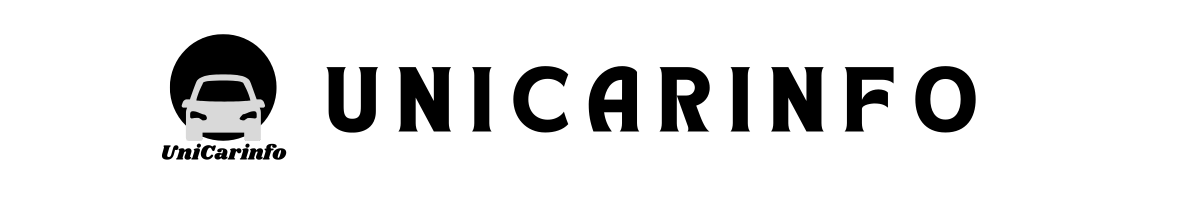レクサスの人気コンパクトSUV、UX。そのモデルチェンジについて、「フルモデルチェンジはいつ?」「2026年に出るって本当?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。次期モデルの予想スペックや燃費、新しいカラー展開への期待が高まる一方、現行モデルの売れ行きや、生産打ち切り・廃盤の噂、さらには一部で聞かれる「ひどい」という評価の真偽も気になるところです。この記事では、2025年現在の最新情報をもとに、レクサスUXのモデルチェンジに関するあらゆる疑問に迫ります。
良質なレクサスUXを中古で効率的に探したい方は、ズバット車販売の中古車無料お探しサービスを利用するのがおすすめです。特に注目すべきは、一般には出回らない非公開車両の情報を入手できる点です。

ズバット車販売のポイントはココ!
✅ 非公開車両の情報が手に入る(一般サイトには出ていない掘り出し物アリ)
✅ 予算や条件を伝えるだけで、専門スタッフがぴったりの車を探してくれる
✅ 独自ネットワークを活用して、コスパの良い中古車が見つかる可能性
✅ 信頼できる業者のみが取り扱い、品質や整備も安心
✅ 無料で利用できて、しつこい営業もナシ!
▼詳しくはこちらのリンクからアクセスできます
レクサスUX モデルチェンジ2025最新情報

- 次期レクサスUX フルモデルチェンジはいつ?
- 2026年登場?次期レクサスUXの予想
- レクサスUX 2025 最新情報まとめ
- 現行UX 生産打ち切りや廃盤の噂は?
- レクサスUX 現行モデルの売れ行き
次期レクサスUX フルモデルチェンジはいつ?

レクサスの人気コンパクトSUVであるUXについて、「次のフルモデルチェンジはいつ頃になるのだろう?」と気になっている方は多いのではないでしょうか。最新の情報やこれまでの傾向から総合的に判断すると、次期レクサスUXのフルモデルチェンジは2026年に行われる可能性が高いと考えられます。
なぜ2026年という時期が有力視されているのでしょうか。背景には、いくつかの理由が考えられます。
- 現行モデルのライフサイクル: 現行の初代レクサスUXは、2018年11月に日本で発売されました。自動車業界における一般的なフルモデルチェンジのサイクルは、およそ6年から8年程度とされています。このサイクルに当てはめると、2024年から2026年あたりが次期モデル登場のタイミングとして自然です。特に近年は電動化技術の進展が目覚ましく、各メーカーともモデルチェンジのサイクルを早める傾向も見られるため、2026年は有力な時期と言えるでしょう。
- レクサスの電動化戦略: レクサスはブランド全体として、カーボンニュートラル社会の実現に向けた電動化を強力に推進しています。2030年までに全カテゴリーでBEV(バッテリー電気自動車)のフルラインアップを実現し、2035年にはグローバルでBEV販売比率100%を目指すという目標を掲げています。この壮大な計画の中で、UXのような量販モデルの電動化シフトは非常に重要です。2026年というタイミングは、次世代の電動化技術を投入するのに適した時期と考えられます。
- 技術革新のタイミング: 自動車技術、特に電動化技術や先進運転支援システム(ADAS)は日進月歩で進化しています。2026年頃には、より高性能なバッテリー、効率的なモーター、高度な自動運転支援技術などが実用化されている可能性が高いです。レクサスとしても、これらの最新技術を新型UXに積極的に投入し、商品力を大幅に向上させたいと考えているはずです。
予想される具体的な登場時期についてですが、いくつかの情報源では「2026年3月頃」という見方も出ています。これは、自動車メーカーが春先に新型モデルを発表・発売することが多いという慣例に基づいている可能性があります。
しかし、これはあくまで現時点での予想に過ぎません。開発の進捗状況や市場の動向、競合他社の動きなどによって、時期が前後する可能性は十分に考えられます。
正式発表はいつ頃になるのでしょうか。フルモデルチェンジのような大きな変更の場合、通常は正式発表の数ヶ月前から徐々に情報が公開され始めます。例えば、コンセプトモデルの発表、ティザーキャンペーン(一部分を見せるなどして期待感を高める手法)、プロトタイプ(試作車)のスパイショット(隠し撮り写真)の流出などが考えられます。
もし2026年初頭の発売が濃厚であれば、2025年の後半あたりから具体的な情報が出始めるかもしれません。東京モーターショー改め「JAPAN MOBILITY SHOW」などの大きなイベントで、何らかの発表が行われる可能性も期待されます。
フルモデルチェンジ時期に関する注意点として強調しておきたいのは、これらの情報はすべて現時点での「予想」や「噂」に基づいているという点です。自動車の開発スケジュールは、様々な要因によって変更されることがあります。
- 世界的な半導体不足の影響: 近年、自動車業界は半導体不足に悩まされており、生産計画に影響が出ています。この問題が長引けば、新型車の開発や発売時期にも遅れが生じる可能性があります。
- 経済状況の変化: 世界経済の動向も無視できません。景気後退などが起これば、メーカーは投資計画を見直し、新型車の投入時期を調整する可能性もあります。
- 開発の難航: 新しい技術を多数盛り込む場合、開発が計画通りに進まないこともあり得ます。特に、ソフトウェア開発の複雑化は、近年多くのメーカーで課題となっています。
したがって、「2026年登場」という情報はあくまで目安として捉え、今後のレクサスからの正式発表を待つことが重要です。焦って現行モデルの購入判断を急いだり、逆に待ちすぎて購入タイミングを逃したりしないよう、最新情報を継続的にチェックすることをおすすめします。
2026年登場?次期レクサスUXの予想

2026年にフルモデルチェンジが予想される次期レクサスUXは、現行モデルから大幅な進化を遂げることが期待されています。単なるデザイン変更にとどまらず、プラットフォームの刷新、パワートレインの全面的な見直し、そして先進技術の積極的な導入など、多岐にわたる変更が噂されています。ここでは、現時点で予想されている次期UXの姿について、詳しく見ていきましょう。
次期UXにおける最大の注目点は、パワートレインの大幅な変更、特に電動化のさらなる推進です。
現行UXにも存在するBEV(バッテリー電気自動車)モデル「UX300e」は、次期モデルで大幅に進化する見込みです。
- 航続距離の延伸: 新開発の大容量バッテリー搭載により、一充電あたりの航続距離が現行の512km(WLTCモード)から大幅に伸びると予想されています。情報源によっては「600km~650km程度」や「最大800km」といった具体的な数値も挙げられており、実用性が飛躍的に向上する可能性があります。
- 出力の向上: モーター出力も向上し、より力強い加速性能を発揮すると考えられます。一部では、フロントとリアにモーターを搭載するデュアルモーターシステムを採用し、システム合計出力が「300ps」や「350ps以上」に達するとの予想もあります。これにより、スポーティーな走行性能が期待できます。
- 充電性能の向上: バッテリー性能の向上に伴い、充電時間の短縮も期待されます。より高出力な急速充電への対応や、バッテリー温度管理システムの改良などが進むと考えられます。
現行の主力であるハイブリッドモデル(HEV)も、システムが一新される可能性があります。
- 新開発1.5Lターボエンジン: 現行の2.0L自然吸気エンジンに代わり、新開発の1.5L直列4気筒ターボエンジンが採用されるとの情報があります。この新エンジンは、小型・軽量でありながら高効率・高出力を実現し、厳しい排ガス規制(ユーロ7など)にも対応するとされています。
- システム出力の向上: 新エンジンと改良されたモーター、バッテリーを組み合わせることで、システム合計出力が現行UX300hの199psから「230ps」程度まで向上するのではないかと予想されています。これにより、動力性能と燃費性能の両立が一層高いレベルで実現されるでしょう。
また、一部の情報では、次期UXはハイブリッドモデルを設定せず、BEV専用車種として生まれ変わる可能性も示唆されています。これはレクサスの電動化戦略をより強く推し進める動きですが、ユーザー層やインフラ整備の状況を考えると、当面はHEVとBEVの両方をラインナップする可能性の方が高いかもしれません。この点は今後の情報に注目が必要です。
次に、新プラットフォーム採用の可能性についてです。次期UXでは、電動化に最適化された新しいプラットフォームが採用されると予想されています。
この新プラットフォームは、バッテリーを床下に効率よく配置できるよう設計され、低重心化による走行安定性の向上に貢献します。また、ホイールベース(前輪と後輪の間の距離)が現行の2640mmから「2700mm」や「2750mm」へと大幅に延長されるとの予測もあり、これにより後席の足元スペースや荷室容量が拡大され、現行モデルの弱点とされていた居住性や実用性が改善されることが期待されます。
ただし、採用されるプラットフォームの種類については、情報が錯綜しています。レクサスが2026年に導入を予定している、ギガキャスト(大型アルミ部品の一体成型技術)を用いた次世代BEV専用プラットフォームが使われるという見方がある一方、現行プリウスなどで採用されているTNGAプラットフォーム(GA-C)をBEV向けに改良したものが用いられるのではないか、という見方もあります。後者の根拠としては、予想されるホイールベース長がプリウス(2750mm)に近いことなどが挙げられます。どちらになるかで、車両の基本骨格や生産効率が大きく変わってくるため、注目されるポイントです。
デザインと空力性能の向上も予想されます。エクステリアデザインも大きく変更される見込みです。
レクサスの最新デザイン言語が反映され、より洗練された、あるいはよりアグレッシブなスタイルになると予想されます。フロントグリルは、現行のスピンドルグリルから、ボディと一体化した「スピンドルボディ」へと進化する可能性があります。また、シャープなヘッドライトや立体的なフェンダー、クーペライクなルーフラインなどが採用され、スポーティさとプレミアム感を両立したデザインが追求されるでしょう。
特にBEVモデルにおいては、航続距離を伸ばすために空力性能の向上が非常に重要になります。ボディ形状の最適化はもちろん、フラットなアンダーボディ、エアロホイールなど、細部にわたる工夫が凝らされると考えられます。デザイン性と空力性能を高次元でバランスさせることが求められます。
先進技術の進化も期待されます。運転支援システムやコネクティビティ機能なども最新世代へと進化します。
- 運転支援システム: 予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」はさらに機能が拡充され、検知範囲の拡大や制御の高度化が進むでしょう。また、高速道路でのハンズオフ運転支援などを含む高度運転支援技術「Lexus Teammate」の搭載も期待されます。
- 新駆動システム: BEVの上位モデルには、四輪の駆動力を緻密に制御する「DIRECT4」が採用される可能性があります。これにより、あらゆる走行シーンで高い安定性とリニアな操舵応答性を実現します。また、ステアリング操作を電気信号で伝える「ステア・バイ・ワイヤ」の採用も噂されており、より自由な車両制御や快適な乗り心地に貢献するかもしれません。
- AI活用: AI技術を活用した次世代の音声認識システムが搭載され、ナビゲーションやオーディオ、エアコンなどの操作がより自然な対話で行えるようになる可能性があります。
予想されるデメリットや懸念点としては、多くの進化が期待される一方で、いくつかの点も考えられます。
- 価格の上昇: プラットフォームの刷新や最新技術の多数採用により、車両価格が現行モデルよりも上昇することは避けられないでしょう。特にBEVモデルは、バッテリーコストの影響で高価になる可能性があります。
- 完全BEV化への賛否: もし完全BEV化された場合、充電インフラや航続距離に不安を感じるユーザーにとっては、選択肢から外れてしまう可能性があります。
- デザインの好み: 大胆なデザイン変更が行われた場合、それがすべてのユーザーに受け入れられるとは限りません。
これらの予想は、現時点での情報を基にしたものです。実際の次期UXがどのような姿で登場するのか、今後の正式発表を楽しみに待ちたいところです。
レクサスUX 2025 最新情報まとめ

2026年のフルモデルチェンジに向けて期待が高まるレクサスUXですが、「2025年現在の最新情報は?」と気になっている方もいらっしゃるでしょう。フルモデルチェンジに関する具体的な公式発表はまだ少ない状況ですが、現行モデルの改良内容や市場の動向から、次期モデルへの期待感を読み取ることができます。ここでは、2025年時点でのレクサスUXに関する情報を整理してお伝えします。
まず、現行UXについて理解を深める上で重要なのが、2023年に行われた大幅な改良です。この改良は、フルモデルチェンジを見据えた布石とも言える内容を含んでおり、商品力を大きく向上させました。
この改良での最も大きな変更点は、ガソリンエンジンモデルが廃止され、ラインナップがハイブリッド(HEV)とバッテリーEV(BEV)のみになったことです。これは、レクサスの電動化戦略を明確に示すものでした。
従来のハイブリッドモデル「UX250h」は、より高性能な「UX300h」へと進化しました。
- システム出力向上: 2.0Lエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムの合計出力が、従来の184PSから199PSへと向上し、より力強くスムーズな加速を実現しました。
- 4WDモデルのリアモーター強化: 4WD(E-Four)モデルに搭載されるリアモーターの出力が、従来の7PS/55N・mから41PS/84N・mへと大幅にパワーアップ。これにより、発進時や旋回時の安定性が向上し、よりダイナミックな走行が可能になりました。
- 燃費性能: WLTCモード燃費は、2WDモデルで24.7km/L~26.3km/L、4WDモデルで23.4km/L~25.2km/Lと、高い環境性能を維持しています。
BEVモデルである「UX300e」も大幅な改良を受けました。
- バッテリー容量増加: 駆動用バッテリーの総電力量が、従来の54.4kWhから72.8kWhへと大容量化されました。
- 航続距離延長: これに伴い、一充電走行距離(WLTCモード)が従来の367kmから512kmへと約40%も向上。日常使いでの利便性が格段にアップしました。
- 充電性能: バッテリークーラー/ヒーターの搭載により、急速充電時の性能安定性や普通充電時間の短縮(AC200V・30Aで約12時間)が図られました。
パワートレイン以外にも、様々な改良が施されました。
- ボディ剛性強化: ラジエーターサポートブレースやロアバックパネル下部のガゼット追加などによりボディ剛性を高め、操縦安定性と乗り心地を向上させました。
- 静粛性向上: ルーフ減衰材の変更や制振材の追加により、車内の静粛性を高めました。
- 先進装備の進化:
- 予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」の機能が拡充され、交差点での衝突回避支援(出会い頭車両、右左折時)や緊急時操舵支援などが追加されました。
- 12.3インチの大型フル液晶メーターや、操作性を向上させたエレクトロシフトマチックが採用されました。
- 非常時給電システム付きアクセサリーコンセント(AC100V・1500W)が設定され、災害時の電源としても活用可能になりました。
2023年の大幅改良以降、2024年から2025年初頭にかけては、UXに関する大きなニュースは比較的少ない状況です。これは、メーカーが次期モデルの開発に注力している時期とも考えられます。市場では、年次改良による装備の小変更や特別仕様車の設定などが行われる可能性はありますが、基本的には2023年改良モデルの仕様が継続されていると考えられます。
この時期は、次期モデルに関する噂や憶測が飛び交いやすくなります。前述のようなパワートレインの予想やデザインに関する情報などが、自動車専門誌やウェブサイトで報じられることが増えるでしょう。ただし、これらは非公式な情報である点に注意が必要です。
2025年時点では、ユーザーや市場の関心は、やはり2026年に予想されるフルモデルチェンジに集まっています。特に注目されているのは以下の点です。
- 電動化の更なる進化は? (BEV航続距離、新HEV性能)
- プラットフォーム刷新による変化は? (室内空間、荷室の広さ)
- デザインはどうなる? (レクサスの新デザイン反映)
- 先進技術は? (最新運転支援、コネクティビティ)
- 価格は? (どの程度上昇するか)
これらの期待や疑問に対し、2025年後半にはメーカーから何らかのヒントが出てくる可能性も考えられます。
フルモデルチェンジが近いとされる2025年は、現行UXの購入を検討している方にとっては悩ましい時期かもしれません。現行モデル購入の判断材料として、モデル末期のメリット・デメリットを挙げておきます。
- モデル末期のメリット:
- 熟成された信頼性: モデルライフを通じて改良が重ねられており、初期トラブルなどのリスクが少ない。
- 値引きへの期待: 新型登場が近づくと、在庫車を中心に値引き交渉がしやすくなる場合がある。
- 納期の安定: 生産が安定しており、比較的早く納車される可能性がある(ただし、グレードやオプションによる)。
- モデル末期のデメリット:
- 陳腐化のリスク: 購入後すぐに新型が登場し、デザインや技術面で見劣りしてしまう可能性がある。
- リセールバリュー: 新型登場後は、現行モデルの中古車価格が下落する傾向がある。
2023年の大幅改良で商品力は大きく向上しているため、現行モデルのデザインや性能に満足しているのであれば、モデル末期のお得な条件で購入するのも一つの選択肢です。一方で、最新技術やデザインを重視するなら、もう少し待って新型の情報を確認してから判断するのが賢明でしょう。ご自身の価値観や予算、クルマの使い方に合わせて慎重に検討することをおすすめします。
現行UX 生産打ち切りや廃盤の噂は?

「レクサスUXは生産打ち切りになるの?」「もしかして廃盤?」といった噂を耳にして、不安に思われている方もいるかもしれません。結論から言うと、2026年に予想されるフルモデルチェンジに伴い、現行モデルの生産は終了しますが、「廃盤」つまりUXという車種自体がなくなってしまう可能性は現時点では低いと考えられます。これは「生産終了」であり、次世代への「モデルチェンジ」と捉えるのが適切でしょう。
モデルチェンジと生産終了の関係について説明します。自動車メーカーは、通常、数年ごとに車種の設計や性能を全面的に見直す「フルモデルチェンジ」を行います。新しいモデル(次期モデル)が登場する際には、それまでのモデル(現行モデル)の生産は段階的に終了していくのが一般的です。これは、新しい技術やデザインを取り入れた新型車にラインナップを切り替えるためであり、ごく自然な流れです。
したがって、次期レクサスUXが登場すれば、現行の初代UXの生産が終了(打ち切り)されること自体は、ほぼ確実と言えます。
ここで、「打ち切り」「廃盤」という言葉のニュアンスについて整理しておく必要があります。
- 生産終了(打ち切り): ある特定のモデル(例: 初代レクサスUX)の生産を止めること。これはモデルチェンジの際にも起こります。
- 廃盤(廃止): その車種名自体がラインナップから消滅すること。後継車種が登場せずに、そのカテゴリーから撤退する場合などが該当します。
レクサスUXの場合、現行モデルの生産は終了しますが、UXという車名とコンパクトSUVとしてのポジションは、次期モデルに引き継がれる可能性が高いと考えられます。つまり、「廃盤」ではなく、世代交代としての「生産終了」と見るべきでしょう。
レクサスUXが「廃盤」になる可能性が低いと考えられる理由は、その市場における重要性にあります。
- エントリーモデルとしての役割: UXは、レクサスブランドの中では比較的手頃な価格帯であり、初めてレクサス車を購入する層や、ダウンサイジングを考える層にとって重要な入口となっています。(※2023年にLBXが登場し、厳密なエントリーモデルの座は譲りましたが、依然として重要なポジションであることに変わりはありません)
- コンパクトSUV市場の人気: 世界的にコンパクトSUVの需要は高く、レクサスとしてもこのセグメントで競争力のあるモデルを持ち続けることは戦略上重要です。
- LBXとの棲み分け: よりコンパクトなLBXが登場したことで、UXは少し上のクラス(Cセグメント)として、LBXとは異なる顧客層にアピールできます。全長や室内空間、想定されるパワートレインの性能などで差別化が図られるでしょう。
これらの理由から、レクサスがUXという人気モデルを完全に廃止するとは考えにくく、フルモデルチェンジによって商品力を強化し、販売を継続していく可能性が高いと言えます。
生産終了時期はいつ頃になるのでしょうか。現行モデルの生産終了時期は、次期モデルの発売時期と密接に関連します。一般的には、次期モデルの正式発表から発売までの間に、現行モデルの生産は徐々に絞られ、最終的にはオーダーストップとなります。
もし次期モデルが2026年3月頃に発売されると仮定すると、現行モデルの注文受付は2025年後半から2026年初頭あたりに終了する可能性があります。ただし、これはあくまで一般的なスケジュールであり、半導体供給状況や在庫状況によって変動します。
現行モデルの生産が終了すると、中古車市場にも影響が出ます。
- 価格の下落: 新型モデルが登場すると、一般的に現行モデルの中古車価格は下落する傾向にあります。特に発売直後は値下がり幅が大きくなる可能性があります。
- タマ数の増加: モデル末期には、新型への乗り換えによる下取り車が増加し、中古車市場での流通量(タマ数)が増える可能性があります。
中古でUXの購入を検討している場合は、生産終了後の市場動向を注視すると、良い条件で購入できるチャンスがあるかもしれません。
もし現行UXを新車で購入したいと考えている場合は、以下の点に注意が必要です。
- 注文期限: 生産終了が近づくと、メーカーオプションやボディカラーなどの選択肢が制限されたり、注文自体ができなくなったりします。希望通りの仕様で購入したい場合は、早めにディーラーに相談することをおすすめします。
- 在庫状況と納期: モデル末期は、ディーラーの在庫車が販売の中心になる場合があります。希望の仕様の在庫がない場合は、納期がかかる、あるいは購入できない可能性もあります。
繰り返しになりますが、現行UXは「廃盤」ではなく、次世代へのモデルチェンジに伴う「生産終了」となる可能性が高いです。過度に心配する必要はありませんが、購入を検討している場合は、今後の情報やディーラーからの案内に注意を払いましょう。
レクサスUX 現行モデルの売れ行き

レクサスUXの現行モデルが、市場でどの程度受け入れられているのか、その「売れ行き」は気になるところです。結論としては、レクサスUXはブランドのエントリークラスを担う重要なモデル(※LBX登場前は主力の एंट्रीモデル)として、発売以来、安定した人気を維持していると言えます。特に都市部での需要が高く、幅広い層から支持を集めています。
レクサス内での販売状況と位置づけについてですが、正確なモデル別販売台数の公式データは常に公開されているわけではありませんが、一般的にレクサスUXは、RXやNXといった上位SUVモデルに次ぐ販売台数を記録している人気車種の一つとされています。
レクサスブランド全体の中では、比較的コンパクトで価格も抑えめな設定(レクサス基準で)であることから、以下のような役割を担っています。
- 新規顧客獲得: 他ブランドからの乗り換えや、初めて高級車を購入する層へのアピール。
- ダウンサイジング需要の受け皿: より大きなセダンやSUVから、取り回しの良いサイズへの乗り換えを考える層の選択肢。
- セカンドカー需要: ファミリーのセカンドカーとしての需要。
2023年末に、よりコンパクトなLBXが登場したことで、「最も小さいレクサスSUV」「最も手頃なレクサス」というポジションはLBXに譲ることになりました。しかし、LBXとは異なるサイズ感やキャラクターを持つUXは、依然としてレクサスのラインナップにおいて重要な存在であり続けています。
なぜレクサスUXは安定した売れ行きを維持しているのでしょうか。その背景には、いくつかの理由が考えられます。
まず、デザインの評価が高い点が挙げられます。
- 都会的でスタイリッシュ: レクサス特有のシャープで洗練されたデザインは、都市部の風景によく映えます。特に若い層や女性からの支持が高いと言われています。
- 高級感: コンパクトながらも、細部の作り込みや素材感にはレクサスらしい高級感が漂います。
次に、ちょうど良いサイズ感も人気の理由です。
- 日本の道路事情にマッチ: 全長約4.5m、全幅約1.84mというサイズは、日本の狭い道路や駐車場でも比較的扱いやすいと評価されています。最小回転半径も輸入車の同クラスSUVと比較して小さい場合が多く、取り回しの良さが魅力です。
- 運転のしやすさ: 見切りの良い視界や、適度なアイポイント(着座位置の高さ)も、運転のしやすさに貢献しています。
そして、レクサスブランドへの信頼性も大きな要因です。
- 高い品質と耐久性: レクサス車は、品質や耐久性、信頼性の高さで定評があります。故障が少なく、長く安心して乗れるというイメージが、購入の決め手となるケースも多いようです。
- 手厚いサポート: 正規ディーラーでの質の高いサービス(おもてなし)や、充実した保証、メンテナンスプログラムなども、ブランドへの信頼感を高めています。
さらに、電動化モデルの選択肢があることも強みです。
- 優れた燃費性能(HEV): ハイブリッドモデル(UX300h)は、優れた燃費性能を誇り、ランニングコストを抑えたいユーザーにとって魅力的です。
- 静粛性とスムーズな走り(HEV/BEV): 電動モーターによる走行は非常に静かで滑らかであり、上質なドライブフィールを提供します。特にBEV(UX300e)は、その静粛性と力強い加速が特徴です。
- 環境性能: 環境意識の高まりから、HEVやBEVといった電動化モデルへの関心が高まっていることも、UXの販売を後押ししています。
加えて、2023年の改良による商品力向上も無視できません。前述の通り、パワートレインの性能向上、航続距離の延長(BEV)、安全装備の拡充、装備の充実化などが図られ、商品力が大きく底上げされたことも、安定した販売につながっていると考えられます。
競合車種との比較ではどうでしょうか。レクサスUXの競合となるのは、メルセデス・ベンツ GLA、BMW X1/X2、アウディ Q2/Q3といった輸入プレミアムコンパクトSUVや、トヨタ ハリアー、マツダ CX-5/CX-30などの国産上位SUVです。
これらの競合と比較した場合、UXはレクサスならではの品質感、信頼性、静粛性、ハイブリッドモデルの燃費性能などが強みとなります。一方で、室内空間(特に後席や荷室)の広さや、走行性能の一部(特にスポーティさ)においては、競合車に分があるという評価も見られます。売れ行きとしては、輸入車勢や国産の人気SUVには及ばないものの、プレミアムブランドのコンパクトSUVとしては健闘していると言えるでしょう。
売れ行きに関する懸念点や今後の予測としては、安定した人気を誇るUXですが、いくつかの点も考えられます。
- LBX登場の影響: よりコンパクトで価格も抑えられたLBXが登場したことで、これまでUXを検討していた一部の顧客層がLBXに流れる可能性は否定できません。両モデルの棲み分けが今後どのように市場に受け入れられていくかが注目されます。
- モデル末期の影響: フルモデルチェンジが近づくと、新型への期待感から買い控えが起こり、一時的に販売台数が落ち込む可能性があります。
- 競争の激化: コンパクトSUV市場は国内外のメーカーが注力しており、競争はますます激しくなっています。次期モデルでさらなる商品力向上が求められます。
とはいえ、レクサスUXは独自の魅力を持つモデルであり、一定の需要は今後も続くと考えられます。2023年の改良で商品力は高められており、モデル末期ながらも選択肢として十分に魅力的です。フルモデルチェンジへの期待も高く、次期モデルが登場すれば、再び販売に勢いがつくことが予想されます。
レクサスUX モデルチェンジ後のスペックと評価

- 新型レクサスUX 予想されるスペック詳細
- 次期レクサスUX 予想される燃費性能
- レクサスUX 新型モデルのカラー展開は?
- 電動化は進む?パワートレインの進化
- デザイン刷新?予想される外観と内装
- レクサスUXの「ひどい」との評価は本当?
新型レクサスUX 予想されるスペック詳細
2026年にフルモデルチェンジが期待されるレクサスUX。そのスペックがどのように進化するのか、多くの関心が集まっています。現時点で明らかになっている情報や様々な予想をもとに、新型レクサスUXのスペック詳細を探っていきましょう。
まず注目したいのはボディサイズです。現行モデル(全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mm、ホイールベース2640mm)に対し、新型ではプラットフォームの刷新に伴い、特にホイールベースが大幅に延長されると見られています。予想される数値としては、
- 全長: 約4500mm (現行並みか微増)
- 全幅: 約1840mm (現行並み)
- 全高: 約1600mm (やや高く)
- ホイールベース: 約2700mm~2750mm (60mm~110mm延長)
といった情報があります。全長や全幅は大きく変えずにホイールベースを伸ばすことで、現行モデルの弱点とされていた後席の足元空間や荷室容量の拡大が期待されます。これは居住性や使い勝手の向上に直結する重要なポイントです。一方で、全高が若干高くなるのは、床下にバッテリーを搭載するBEV(電気自動車)モデルの地上高を確保するためかもしれません。サイズ変更による取り回しへの影響は最小限に抑えつつ、実用性を高める狙いがあると考えられます。
次にプラットフォームです。次期UXでは、電動化への対応を主眼に置いた新しいプラットフォームが採用される可能性が高いです。これが、レクサスが開発を進めるギガキャスト技術を用いた次世代BEV専用プラットフォームなのか、あるいは既存のTNGAプラットフォーム(GA-C)をベースに電動化対応を進化させたものなのかは、現時点では情報が分かれています。いずれにしても、バッテリー搭載に最適化され、低重心化や高剛性化が図られることで、走行性能の向上が期待できます。プラットフォームの刷新は、乗り心地や操縦安定性、静粛性といった車の基本性能を大きく左右するため、非常に重要な変更点と言えるでしょう。
シャシーやサスペンションにも改良が加えられるはずです。ボディ剛性のさらなる向上は、ドライバーの意図に忠実なハンドリングや、高速走行時の安定感につながります。サスペンションも、新しいプラットフォームに合わせて最適化され、よりしなやかで上質な乗り心地と、スポーティな走行を両立するセッティングが追求されると予想されます。
そして、先進装備や機能の進化も見逃せません。
- 安全装備: 最新の予防安全パッケージ「Lexus Safety System +」が搭載され、検知能力や対応範囲がさらに拡大されるでしょう。高速道路でのハンズオフ運転支援などを含む「Lexus Teammate」の採用も期待されます。
- 駆動システム: BEVモデルには、四輪の駆動力を自在に制御する「DIRECT4」が搭載される可能性があります。これにより、発進加速からコーナリング、制動時まで、常に最適な駆動力配分を行い、高い走行安定性とダイレクトな操作感を実現します。
- ステアリング: ステアリングホイールとタイヤを電気信号でつなぐ「ステア・バイ・ワイヤ」の採用も噂されています。これが実現すれば、路面からの不要な振動を遮断しつつ、速度に応じて最適な操舵フィールを提供することが可能になります。
- AI活用: AI技術を活用した音声認識システムは、より自然な対話での車両操作を可能にし、コネクティビティ機能も強化され、利便性が向上すると考えられます。
これらのスペックは、あくまで現時点での予想や情報に基づいています。特にプラットフォームの種類やパワートレインの最終仕様などは、正式発表まで確定しません。しかし、これらの予想から、次期レクサスUXが基本性能から先進技術に至るまで、全方位的な進化を遂げる可能性が高いことがうかがえます。今後の公式情報に注目していきましょう。
次期レクサスUX 予想される燃費性能

自動車を選ぶ上で、燃費性能(電気自動車の場合は電費)は、環境への配慮はもちろん、日々のランニングコストにも直結する重要な要素です。フルモデルチェンジが予想される次期レクサスUXでは、この燃費・電費性能がどのように進化するのか、見ていきましょう。
まず、ハイブリッドモデル(HEV)の燃費についてです。次期UXでは、現行の2.0L自然吸気エンジンベースのシステムから、新開発の1.5Lターボエンジンを核とした新世代ハイブリッドシステムへ移行する可能性があります。この新しいシステムは、エンジンの熱効率向上やハイブリッド制御の最適化により、さらなる燃費向上が期待されています。
いくつかの情報源では、具体的な予想燃費値(WLTCモード)として、
- FF(前輪駆動)モデル: 約27.5km/L
- 4WD(四輪駆動)モデル: 約26.5km/L といった数値が挙げられています。
現行モデル(UX300h)のWLTCモード燃費が、2WDで24.7km/L~26.3km/L、4WDで23.4km/L~25.2km/Lであることを考えると、特に4WDモデルでの向上が見込まれます。これは、システム出力の向上(199ps→230ps予想)を果たしつつも、燃費性能も改善するという、技術的な進化を示すものです。燃費向上の要因としては、高効率な新エンジンの採用、モーターやバッテリーを含むハイブリッドシステム全体の効率アップ、そして後述する空力性能の改善などが複合的に寄与すると考えられます。
次に、バッテリーEV(BEV)モデルの「電費」についてです。電気自動車の場合、ガソリン車の燃費に相当する指標として「電費」(交流電力量消費率、単位はWh/km)がありますが、一般的には「一充電走行距離(航続距離)」の方が注目されます。次期UXのBEVモデルでは、この航続距離が大幅に向上すると予想されています。
現行UX300eの航続距離は512km(WLTCモード)ですが、次期モデルでは新開発の大容量バッテリー(80kWhクラスとの情報も)の搭載やエネルギー効率の改善により、「600km~650km」あるいは「最大800km」に達するのではないか、と見られています。航続距離が伸びるということは、より少ない電力でより長い距離を走れる、つまり実質的な「電費」が向上することを意味します。バッテリー容量の増加だけでなく、モーターの効率改善、軽量化、そして空力性能の向上が、航続距離の延伸に貢献すると考えられます。
ただし、燃費や電費(航続距離)は、様々な要因によって変動することも理解しておく必要があります。
- 車両重量: オプション装備の有無や乗車人数、積載する荷物の量によって車両重量は変わり、燃費・電費に影響します。
- タイヤサイズ: 一般的に、タイヤサイズが大きくなると転がり抵抗が増え、燃費・電費には不利になる傾向があります。グレードによって装着されるタイヤサイズが異なる場合があります。
- 運転スタイル: 急発進・急加速・急ブレーキを避ける、エコドライブを心がけることで、燃費・電費は大きく改善します。
- 走行環境: 市街地走行、高速道路走行、渋滞の有無、アップダウンの多い道など、走行する環境によって燃費・電費は変動します。
- エアコンの使用: エアコン(特に暖房)の使用は、燃費・電費に影響を与えます。特にBEVの場合、暖房による電力消費は航続距離を縮める大きな要因となります。
カタログに記載されているWLTCモード燃費や航続距離は、国際的に統一された試験方法に基づいて測定された数値ですが、あくまで一定の条件下での目安です。実際の走行では、上記の要因によって数値が変動することを念頭に置いておく必要があります。
とはいえ、次期レクサスUXでは、ハイブリッドモデルの燃費、BEVモデルの航続距離(電費)ともに、現行モデルから着実な進化が期待できると言えるでしょう。環境性能と経済性を両立させ、より魅力的なモデルとなることが予想されます。
レクサスUX 新型モデルのカラー展開は?

車の第一印象を大きく左右し、オーナーの個性を表現する要素でもあるボディカラー。フルモデルチェンジが噂されるレクサスUXでは、どのようなカラーラインナップが登場するのでしょうか。まだ正式な発表はありませんが、これまでのレクサスのカラートレンドや、最新モデルの動向から予想してみましょう。
まず参考に、現行レクサスUXのカラーラインナップを見てみます。(※時期によって変更がある可能性があります) 代表的な色としては、
- ソニッククォーツ: レクサスを象徴する白系のカラー。陰影を際立たせる独特の輝きが特徴。
- ソニックチタニウム: ソニッククォーツ同様、金属的な質感を表現したシルバー系。
- グラファイトブラックガラスフレーク: 深みのある定番のブラック。
- マダーレッド: 鮮やかさと深みを両立した赤系。
- セレスティアルブルーガラスフレーク: 上品で落ち着いた青系。
- ソニッククロム: 金属感を強調した個性的なシルバー系。
- ブレージングカーネリアンコントラストレイヤリング: オレンジ系の華やかなカラー(メーカーオプション)。 などが設定されています。また、スポーティグレードの「F SPORT」には、専用色としてホワイトノーヴァガラスフレークやヒートブルーコントラストレイヤリングなどが用意されることもあります。
これらの現行色を踏まえつつ、新型モデルのカラー展開を予想してみましょう。
レクサスは近年、独自の塗装技術「ソニック技術」を進化させ、金属質感や陰影表現にこだわったカラーを多く導入しています。新型UXでも、このソニック系のカラーが中心となる可能性が高いです。既存のソニッククォーツやソニックチタニウムが継続されるか、あるいはさらに表現力を高めた新しいソニック系のカラーが登場するかもしれません。例えば、より深みや粒子感を増したブラックやグレー系のソニックカラーなどが考えられます。
また、最近のレクサスの新型車(例えばLBXなど)では、「バイトーンカラー」(ルーフとボディの色が異なる2トーンカラー)が設定されるケースが増えています。コンパクトでスタイリッシュなUXのキャラクターを考えると、新型でもバイトーンカラーがオプション設定され、よりパーソナルでファッショナブルな選択肢が増える可能性は十分にあります。
有彩色についても、新しい提案が期待されます。レクサスは、自然現象や日本の伝統色などからインスピレーションを得た、深みのある独特の色合いを開発することがあります。新型UXでも、例えば落ち着きのあるグリーン系や、エレガントなカッパー(銅色)系、あるいは新しいニュアンスのブルー系などが登場するかもしれません。
もちろん、「F SPORT」グレードには、引き続き専用のスポーティなカラー(鮮やかなブルーやレッド、あるいは専用のホワイトやブラックなど)が設定される可能性が高いでしょう。
カラー選びは、車の印象だけでなく、様々な側面も考慮したいポイントです。
- 人気色・定番色: ホワイト、ブラック、シルバー系は一般的に人気が高く、飽きがこない、汚れが比較的目立ちにくい(色による)といったメリットがあります。
- リセールバリュー: 一般的に、人気色・定番色は中古車市場でも需要が高く、リセールバリュー(売却時の価格)が有利になる傾向があります。個性的な色は、好みが分かれるためリセールでは不利になることも。
- 手入れのしやすさ: 濃色系(ブラックなど)は洗車キズや汚れが目立ちやすく、淡色系(シルバーなど)は比較的目立ちにくいと言われます。ただし、塗装の質やコーティングによっても異なります。
- 個性の表現: 他の人と違う色を選びたい、自分の好みを反映させたいという場合は、思い切って個性的な色を選ぶのも良いでしょう。
インテリアカラーとの組み合わせも重要です。エクステリアカラーとインテリアカラーのコーディネートによって、車全体の雰囲気は大きく変わります。新型UXでも、複数のインテリアカラーが用意され、エクステリアとの組み合わせを選べるようになるでしょう。
現時点では、新型レクサスUXの具体的なカラーラインナップは全くの未定です。しかし、レクサスがこれまで培ってきた塗装技術や色彩表現へのこだわりから、きっと魅力的で多彩なカラーバリエーションが登場することでしょう。正式な発表を楽しみに待ちたいですね。
電動化は進む?パワートレインの進化
「電動化」は、現在の自動車業界における最大のキーワードであり、レクサスブランドにとっても最重要戦略の一つです。コンパクトSUVであるUXも、その流れの中で重要な役割を担っています。次期レクサスUXでは、この電動化がさらに推し進められ、パワートレインが大幅に進化することが確実視されています。
レクサスの電動化戦略を改めて確認しておきましょう。レクサスは、2030年までにすべてのカテゴリーでBEV(バッテリー電気自動車)のフルラインナップを実現し、2035年にはグローバルでのBEV販売比率100%達成を目指しています。この目標達成のため、各モデルの電動化が急ピッチで進められています。UXも例外ではなく、2023年の改良で既にガソリンモデルを廃止し、HEV(ハイブリッド)とBEVのみのラインナップとなっています。次期モデルでは、この電動化がさらに加速する見込みです。
特に注目されるのが、BEVモデルの大幅な進化です。
- 圧倒的な航続距離: 現行UX300eの512km(WLTCモード)から、次期モデルでは「600km~650km」、あるいは「最大800km」へと、飛躍的な向上が予想されています。これは新開発の大容量バッテリー(80kWhクラス?)と、エネルギー効率の改善によって実現されると考えられます。日常使いでの充電頻度を減らし、長距離ドライブへの不安を大きく軽減するでしょう。
- パワフルな走行性能: モーター出力も大幅に向上し、「300ps」や「350ps以上」といったスペックが噂されています。さらに、前後にモーターを搭載するデュアルモーター式の四輪駆動(AWD)システム「DIRECT4」の採用も有力視されており、力強い加速と高い走行安定性を両立することが期待されます。
- 充電性能の向上: より高出力な急速充電への対応や、バッテリーマネジメントシステムの進化により、充電時間の短縮も期待できます。
ハイブリッドモデル(HEV)も、単なる継続ではなく、中身が一新される可能性があります。
- 新世代ハイブリッドシステム: 現行の2.0L自然吸気エンジン+モーターのシステムから、新開発の「1.5L直列4気筒ターボエンジン」をベースとしたシステムへと進化するとの情報があります。この新エンジンは、小型・軽量でありながら高い熱効率と出力を両立し、将来の厳しい排ガス規制にも対応可能とされています。
- システム出力と燃費の両立: システム全体の合計出力は、現行の199psから「230ps」程度へと向上すると予想され、より余裕のある動力性能を発揮するでしょう。同時に、燃費性能も現行モデル同等か、それ以上に改善される(WLTCモードで26km/L~27km/L台予想)と考えられており、走行性能と経済性の高次元での両立が期待されます。
一部では、次期UXがハイブリッドモデルを持たず、完全にBEV専用車種になるのではないか、という可能性も報じられています。これはレクサスの電動化への強い意志を示すものですが、現時点での充電インフラの整備状況や、ユーザーの多様なニーズを考えると、当面はHEVとBEVの両方をラインナップする可能性の方が高いかもしれません。
電動化が進むことによるメリットは多岐にわたります。
- 走行性能: モーター駆動による静かで滑らかな走り、俊敏なレスポンス、力強い加速。
- 環境性能: CO2排出量の削減(HEV)、走行中の排出ガスゼロ(BEV)。
- 維持費: 税制優遇(エコカー減税、CEV補助金など)、燃料代(ガソリン代/電気代)の削減。
一方で、電動化にはまだ課題や注意点も存在します。
- 車両価格: 一般的に電動化モデルは、ガソリン車に比べて車両価格が高くなる傾向があります。特にBEVはバッテリーコストが大きいです。
- 充電インフラ(BEV): 自宅に充電設備がない場合や、長距離移動時の充電場所・時間に不安を感じる可能性があります。
- バッテリーの寿命・交換コスト: 長期間使用した場合のバッテリーの劣化や、将来的な交換費用も考慮する必要があります(ただし、近年バッテリーの耐久性は向上しています)。
次期レクサスUXは、HEV、BEVともに大きな進化を遂げ、電動化時代のコンパクトプレミアムSUVとして、その魅力をさらに高めることが予想されます。どちらのパワートレインを選ぶかは、ユーザーのライフスタイルや価値観によって異なりますが、いずれにしても環境性能と走行性能を高いレベルで両立したモデルとなることは間違いないでしょう。
デザイン刷新?予想される外観と内装
車の購入を検討する際、スペックや性能と同じくらい、あるいはそれ以上に気になるのがデザインではないでしょうか。毎日目にし、乗り込むものだからこそ、気に入ったデザインであることは重要です。フルモデルチェンジが予想される次期レクサスUXでは、外観(エクステリア)も内装(インテリア)も大幅に刷新されることが期待されています。どのようなデザインになるのか、予想されるポイントを見ていきましょう。
まずエクステリアデザインです。近年のレクサスデザインの象徴であった「スピンドルグリル」は、新しいデザイン言語「スピンドルボディ」へと進化していく流れにあります。これは、グリルというパーツ単体ではなく、ボディ全体の造形でスピンドル形状を表現しようとする考え方です。新型RXやLBXで見られるように、グリル部分がボディ同色に近づいたり、シームレスに融合したりするデザインが、次期UXにも採用される可能性があります。これにより、より未来的でクリーンなフロントマスクになるかもしれません。
ヘッドライトやテールランプのデザインも、レクサスのアイデンティティを示す重要な要素です。L字型のデイタイムランニングライトは継承されつつ、さらにシャープで薄型のデザインになることが予想されます。ヘッドライト本体も、高性能なプロジェクター式(3眼タイプなど)が採用され、先進性を強調するでしょう。リアコンビネーションランプは、現行UXでも特徴的な左右一体型(一文字ランプ)ですが、これがさらに洗練された意匠で継続されるか、あるいは新たな表現が用いられるか注目されます。
ボディ全体のフォルムについては、現行モデルの持つ都会的でクーペライクなSUVのイメージを踏襲しつつ、より立体的でダイナミックな造形が与えられる可能性があります。フェンダーの張り出しを強調したり、サイドのキャラクターラインを印象的にしたりすることで、力強さや凝縮感を表現するかもしれません。また、BEVモデルの性能向上には空力性能が不可欠なため、ボディ表面の凹凸を減らすフラッシュサーフェス化や、空気の流れを整えるエアロパーツのデザインなどが、より積極的に取り入れられると考えられます。
次にインテリアデザインです。レクサスは近年、「Tazuna Concept(手綱コンセプト)」と呼ばれる、人と車が直感的につながることを目指したコクピットデザインを推進しています。これは、運転に必要な操作系のスイッチ類をステアリング周辺にまとめ、視線移動や手指の動きを最小限に抑えることで、運転に集中できる環境を作り出す考え方です。次期UXのインテリアも、このコンセプトに基づいて設計される可能性が高いでしょう。
ドライバーの正面には、大型のフル液晶メーターが配置され、走行情報やナビゲーション、運転支援システムの作動状況などを分かりやすく表示します。センターコンソールには、大型のタッチディスプレイが搭載され、ナビやオーディオ、エアコンなどの操作を集約。物理的なスイッチは最小限に抑えられ、すっきりとした先進的なインパネ周りになることが予想されます。
素材感や質感の向上も、レクサスインテリアの重要なポイントです。新型UXでも、上質なレザーや手触りの良いソフトパッド、金属調加飾、精緻なステッチなどが用いられ、プレミアムコンパクトSUVにふさわしい、居心地の良い空間が演出されるでしょう。アンビエントライト(間接照明)なども効果的に使われ、夜間の雰囲気を高めるかもしれません。
そして、ホイールベースの延長によって期待される室内空間の広がりも、インテリアデザインの印象を左右します。特に後席の足元スペースが拡大されれば、より快適にくつろげる空間となります。荷室についても、形状の工夫や容量拡大により、使い勝手が向上することが期待されます。
コネクティビティ機能やAI音声認識システムの進化も、インテリアデザインと密接に関わってきます。よりシームレスにスマートフォンと連携したり、自然な対話で様々な機能を操作できたりするよう、インターフェースがデザインされるでしょう。
デザインの変更は、常に期待と同時に、好みが分かれるという側面も持ち合わせています。次期UXのデザインが、より多くのユーザーに受け入れられる、先進的かつ魅力的なものになることを期待したいですね。
レクサスUXの「ひどい」との評価は本当?
インターネットでレクサスUXについて検索していると、時折「ひどい」といったネガティブなキーワードを目にすることがあり、不安に感じる方もいるかもしれません。本当にレクサスUXは「ひどい」車なのでしょうか? このような評価が出てくる背景と、その真偽について考えてみたいと思います。
まず、「ひどい」と言われる可能性がある点として、主に現行モデル(特に初期型や改良前)に対して指摘されがちなポイントをいくつか挙げてみましょう。
- 後席や荷室の狭さ: これは、レクサスUXについて最もよく聞かれる不満点の一つかもしれません。デザインを優先したクーペライクなフォルムの影響もあり、特に後席の頭上空間や足元スペース、そして荷室容量は、同クラスのSUVと比較してやや狭いと感じるユーザーがいます。大人4人が長時間快適に乗る、あるいは大きな荷物を頻繁に積むといった用途には、確かに少し物足りなさを感じる可能性があります。具体的な荷室容量は、デッキボード下段時で約310L(FF車)と、クラス標準かやや小さめです。
- パワートレインの力不足感: 2023年の改良以前に設定されていた2.0Lガソリンモデルや、初期のハイブリッドモデル(UX200/UX250h)に対して、「加速が物足りない」「高速走行時の余裕がない」といった声がありました。特に車重に対してエンジンの力がやや非力に感じられた場面があったのかもしれません。ただし、前述の通り2023年の改良でハイブリッドシステムは「UX300h」へと進化し、システム出力が向上したことで、この点は改善されています。
- 価格設定: レクサスブランドの中ではエントリーモデルに位置づけられますが、それでも車両価格は約450万円からと、決して安価ではありません。同クラスの国産SUVや、一部の輸入車と比較した場合、「価格の割に装備が…」あるいは「この価格ならもう少し室内が広くても…」といった意見が出ることもあります。コストパフォーマンスを重視するユーザーにとっては、割高に感じられる可能性はあります。
- 乗り心地: 発売当初のモデルに対して、一部で「乗り心地が硬め」といった評価がありました。スポーティな走りを意識したセッティングだったのかもしれませんが、路面の凹凸を拾いやすいと感じる人もいたようです。これも年次改良などで改善が図られている部分です。
- ナビ・操作系: 2022年の改良以前のモデルでは、センターディスプレイの操作にタッチパッド式のリモートタッチが採用されていました。これについては、「操作がしにくい」「直感的でない」といった不満の声が多く聞かれました。現在はタッチディスプレイ式に変更され、操作性は大幅に改善されています。
このように、いくつかの点については、ユーザーの期待値や使い方によってはネガティブな評価につながる可能性があったことは事実です。
しかし、これらの点を捉えて「ひどい」と断じるのは、少し短絡的かもしれません。なぜなら、レクサスUXには、これらの点を補って余りある魅力や、高く評価されている点も多数存在するからです。
- デザイン: 都会的でスタイリッシュなデザインは、依然として多くの人々を惹きつけています。
- サイズ感: 日本の道路環境での扱いやすさは大きなメリットです。
- 品質と信頼性: レクサスならではの高い品質、耐久性、故障の少なさは、大きな安心感につながります。
- 燃費性能(HEV)と静粛性: ハイブリッドモデルの優れた燃費と、電動走行時の静かで滑らかな走りは高く評価されています。
- ブランドイメージとサービス: レクサスブランドが持つ高級感や、ディーラーでの手厚いおもてなしも、満足度を高める要素です。
結局のところ、車に対する評価は、その人の価値観、何を重視するか、どのような使い方をするか、何を比較対象とするかによって大きく異なります。「後席の広さはあまり重視しない」「デザインが何より気に入っている」「レクサスの信頼性が最優先」という人にとっては、UXは非常に満足度の高い車になり得ます。
インターネット上の「ひどい」といった情報は、個人の主観的な意見や、特定の状況下での不満が切り取られている場合も多く、鵜呑みにするのは危険です。玉石混交の情報の中から、自分にとって重要な情報を見極める必要があります。
そして、次期レクサスUXでは、現行モデルで指摘された弱点、特に室内空間の狭さなどが改善されることが大いに期待されています。
もしレクサスUXの購入を検討しているなら、ネット上の評判だけで判断せず、ぜひ実際に試乗してみることを強くおすすめします。自分の目で見て、触れて、運転してみて、自身の感覚で評価することが最も重要です。その上で、メリットとデメリットを比較検討し、自分のライフスタイルや価値観に合っているかどうかを判断するのが良いでしょう。