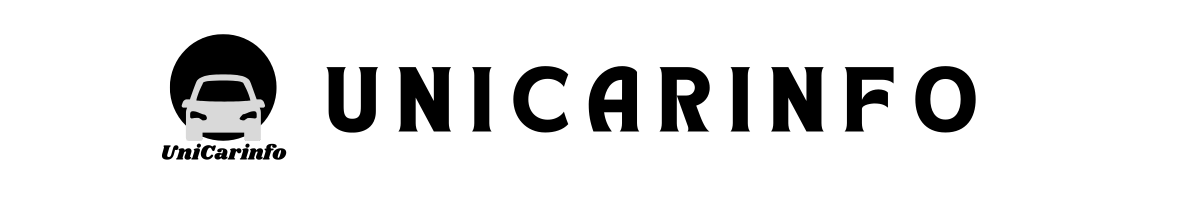「駐車違反をしてしまったけど、点数はどうなるの?」「ゴールド免許を維持したいけど、駐車違反で影響はある?」「出頭しないほうがいいと聞いたけど、デメリットはないの?」「罰金の納付書がいつまで経っても来ない場合、どうすればいい?」など、駐車違反に関する疑問や不安は尽きませんよね。特に、反則金を支払えば点数が引かれないケースがあるという話は、知恵袋などでも話題になっています。しかし、その仕組みや条件を正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。
この記事では、「駐車違反で点数が引かれない」は本当なのか、そのカラクリや、万が一駐車違反をしてしまった場合の対処法、罰金の金額、軽自動車の場合の扱い、ステッカーを貼られた際の注意点、そして気になる違反点数がいつ消えるのかまで、網羅的に解説します。正しい知識を身につけ、万が一の事態に備えましょう。
駐車違反で点数が引かれない!そのカラクリと注意点

駐車違反で点数が引かれないのはなぜ?仕組みを解説
駐車違反をすると、通常は交通違反として反則点数が科され、反則金の納付が必要になります。しかし、「駐車違反をしても点数が引かれなかった」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。これは一体なぜなのでしょうか。
放置車両確認標章と出頭要請
まず、駐車違反が確認されると、車両に「放置車両確認標章(黄色いステッカー)」が取り付けられます。この時点では、まだ運転者は特定されていません。 その後、警察から車両の使用者(通常は車検証に記載されている所有者や使用者)宛に、出頭して反則金を納付するよう求める通知(仮納付書や出頭要請通知)が送られてくるのが一般的でした。運転者が出頭し、違反を認めると、運転者に対して反則点数が科され、反則金を納付することになります。
出頭しない場合は「放置違反金」
ここがポイントです。2006年の道路交通法改正により、運転者が出頭しない場合、車両の「使用者」に対して「放置違反金」の納付が命じられる制度が導入されました。 運転者が特定できない(出頭しない)ため、運転者に対する行政処分である反則点数を科すことができません。その代わりに、車両の管理責任を問い、使用者に対して金銭的な負担を求めるのが「放置違反金」です。
点数が引かれないケースとは?
つまり、運転者が出頭せずに、車両の使用者が放置違反金を納付した場合、運転者に対する反則点数は科されないのです。これが「駐車違反をしても点数が引かれなかった」という状況の主な理由です。
- 運転者が出頭した場合: 運転者に反則点数 + 反則金の納付
- 運転者が出頭せず、使用者が放置違反金を納付した場合: 使用者に放置違反金の納付(運転者に反則点数はなし)
なぜこのような制度になったのか?
この制度変更の背景には、駐車違反の取り締まりを強化し、悪質な駐車違反を減らす狙いがあります。従来は、運転者が出頭しなければ処分が難しくなるケースがありましたが、使用者責任を問うことで、より確実に違反に対する措置を行えるようになりました。
このように、「駐車違反で点数が引かれない」という状況は、運転者が出頭せず、車両の使用者が代わりに放置違反金を納付した場合に起こり得ます。しかし、これにはデメリットや注意点も存在するため、次の見出しで詳しく解説していきます。
「駐車違反しても出頭しないほうがいい」は本当?

「駐車違反をしたら、警察に出頭しない方が点数が引かれなくて得だ」という話を耳にすることがあります。これは、前述の通り、運転者が出頭しなければ車両の使用者に対して「放置違反金」が課され、運転者自身の違反点数は加算されないケースがあるためです。しかし、この選択が本当に「良い」ことなのか、様々な側面から考える必要があります。
出頭しない場合のメリットとデメリット
まずは、出頭しない場合のメリットとデメリットを整理してみましょう。
- メリット
- 運転者自身の違反点数が加算されない(ゴールド免許を維持したい場合など)。
- 警察署に出向く手間と時間が省ける。
- デメリット
- 放置違反金の金額
一般的に、反則金よりも放置違反金の方が高額になる傾向があります。 - 車両の使用制限
短期間に何度も放置違反金を納付するようなことがあると、その車両に対して一定期間使用が禁止される「車両使用制限命令」が出されることがあります。これは法人名義の車だけでなく、個人名義の車も対象です。 - 車検拒否
放置違反金を滞納していると、車検の際に車検証の返付を受けられない(車検に通らない)ことがあります。 - 財産の差し押さえ
放置違反金を長期間滞納し続けると、最終的には財産を差し押さえられる可能性もあります。 - 社会的信用の低下(法人の場合など)
企業が社用車で頻繁に放置違反金の納付を繰り返していると、コンプライアンス意識の低さを問われる可能性があります。
- 放置違反金の金額
※2〜4つ目はよっぽどないと思いますけどね。
「出頭しない方がいい」と言われる背景
それでも「出頭しない方がいい」と言われるのは、主に以下の理由からでしょう。
- 違反点数を避けたい: 特にゴールド免許保持者や、違反点数が累積すると免許停止・取り消しになる可能性がある人にとっては、点数がつかないことは大きな魅力に映ります。
- 手続きの簡便さ: 放置違反金の納付書が送られてきたら、金融機関などで支払うだけで手続きが完了するため、警察署に出頭するよりも手間がかからないと感じる人もいます。
状況に応じた判断が重要
一概に「出頭しない方がいい」とは言えません。例えば、以下のようなケースでは慎重な判断が求められます。
- 他人が運転していた場合: 自分が運転していないにもかかわらず、使用者として放置違反金を納付すると、本来の運転者の責任が曖昧になります。
- 違反内容に納得がいかない場合: 駐車違反の事実に納得がいかない場合は、出頭して自身の主張を伝える機会を持つことも考えられます。ただし、この場合は弁明通知書が送られてきた際の手続きとなり、単なる出頭とは異なります。
- 短期的なメリットと長期的なリスク: 点数がつかないという短期的なメリットと、車両使用制限や車検拒否といった長期的なリスクを天秤にかける必要があります。
結局のところ、「駐車違反で出頭しないほうがいい」という言葉は、特定の状況下でのみメリットがある可能性を示唆しているに過ぎません。安易に判断せず、デメリットやリスクを十分に理解した上で、個々の状況に合わせて総合的に判断することが重要です。駐車違反をしないことが最も大切であることは言うまでもありません。
駐車違反で出頭しないデメリットも確認しよう

前の見出しで、「駐車違反で出頭しないほうがいい」という話の背景と、それが一概には言えないことを説明しました。ここでは、改めて駐車違反で出頭しないデメリットに焦点を当てて、より具体的にどのような不利益が生じる可能性があるのかを確認していきましょう。
1. 金銭的負担の増加:放置違反金は割高になることも
運転者が出頭して反則金を納付する場合と、出頭せずに使用者として放置違反金を納付する場合では、金額が異なることがあります。一般的に、放置違反金の方が反則金よりも高額に設定されていることが多いです。
例えば、普通車の場合、駐停車禁止場所等での放置駐車違反(駐禁)の反則金が15,000円であるのに対し、放置違反金は18,000円となることがあります(金額は違反場所や車両の種類によって異なります)。
目先の点数を気にして出頭しない選択をすると、結果的により多くのお金を支払うことになる可能性があるのです。
2. 車両の使用制限命令のリスク
放置違反金の納付を繰り返すと、その車両に対して「車両使用制限命令」が出されることがあります。これは、一定期間(例えば3ヶ月以内)、その車両を使用してはならないという行政処分です。
具体的には、公安委員会が定める期間内に、同一車両が繰り返し放置違反金の納付命令を受けた場合に対象となります。回数の目安としては、おおむね6ヶ月以内に3回以上、あるいは1年以内に特定の回数以上などが都道府県によって定められています。
通勤や業務で車が不可欠な人にとっては、車両が使用できなくなることは非常に大きな打撃となります。
3. 車検拒否制度:放置違反金滞納のペナルティ
放置違反金を納付せずに滞納していると、車検の際に自動車検査証(車検証)の返付を受けることができません。つまり、車検を更新できず、その車両を公道で運転することができなくなります。
これは「車検拒否制度」と呼ばれ、放置違反金の徴収を確実にするための措置です。車検が切れた車で公道を走行すると、無車検運行となり、さらに厳しい罰則(違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。
4. 財産の差し押さえ
放置違反金の納付命令を受けてもなお支払いを怠り続けると、最終的には地方税の滞納処分と同様の手続きにより、預金や給与、自動車などの財産が差し押さえられる可能性があります。
単なる交通違反と軽く考えていると、生活に深刻な影響を及ぼす事態になりかねません。
5. 運転者の責任が曖昧になる可能性
特に友人や家族に車を貸していた場合や、社用車を従業員が運転していた場合など、運転者と使用者が異なるケースで運転者が出頭しないと、本来違反行為を行った運転者の責任が問われず、使用者であるあなたが放置違反金を支払うことになります。
これにより、運転者の交通安全意識が向上しにくいという問題も考えられます。
6. 繰り返すと「常習性あり」と見なされる
一度や二度の放置違反金納付であれば、違反点数がつかないメリットを享受できるかもしれません。しかし、これを何度も繰り返していると、警察や公安委員会から「常習的な違反者」あるいは「車両の管理責任を果たしていない使用者」と見なされるリスクが高まります。その結果、前述の車両使用制限命令がより出やすくなるなどの不利益につながる可能性があります。
このように、「駐車違反で出頭しない」という選択には、一時的な点数回避というメリットの裏に、多くのデメリットが潜んでいます。これらのリスクを総合的に理解し、安易な判断は避けるべきです。
駐禁ステッカーで罰金なしは可能?黄色の標章の意味

駐車違反をすると、フロントガラスなどに黄色い「放置車両確認標章」(通称:駐禁ステッカー、黄色いステッカー)が貼られます。このステッカーを見て、「罰金なしで済ませる方法はないか?」と考える人もいるかもしれません。
放置車両確認標章とは?
まず、この黄色いステッカーは「罰金(反則金や放置違反金)を課す」という決定通知そのものではありません。これは、「この車両が放置駐車違反として確認された」という事実を告知し、車両の使用者に対して速やかに車両を移動させることを促すためのものです。
標章には、違反日時、場所、車両番号、そして最も重要な「出頭して反則告知を受けるか、後日送付される納付書で放置違反金を納付するか」といった趣旨の案内が記載されています。
「駐禁ステッカーを貼られて罰金なし」は基本的に不可能
結論から言うと、放置車両確認標章が貼られた時点で、何らかの金銭的ペナルティ(反則金または放置違反金)を免れることは基本的にできません。
ステッカーが貼られたということは、警察官や駐車監視員によって駐車違反の事実が現認された証拠です。この現認に基づいて、後日、運転者が出頭すれば反則金の手続きが、出頭しなければ車両の使用者に対して放置違反金の納付命令がなされます。
「ステッカーを剥がしてしまえばバレないのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、標章の情報はすでに警察のシステムに登録されています。ステッカーを剥がしても、違反の記録が消えるわけではありません。
例外的に「罰金なし」となる稀なケースとは?
ごく稀に、以下のような特殊な状況下では、結果的に金銭的な負担が発生しない、あるいは取り消される可能性がゼロではありません。
- 弁明が認められた場合
放置車両確認標章が貼られた後、車両の使用者には「弁明通知書」と「仮納付書(放置違反金)」が送られてくることがあります。この弁明通知書に対して、天災や盗難、その他やむを得ない理由があったと主張し、その弁明が公安委員会に認められた場合には、放置違反金の納付命令がされないことがあります。しかし、弁明が認められるのは非常に限定的なケース(例:車両が盗難に遭っていた、災害により移動できなかったなど、使用者や運転者に責任がないと明確に証明できる場合)に限られ、単に「少しの時間だった」「知らなかった」といった理由では認められないことがほとんどです。 - 警察側の手続きミスなど(極めて稀)
これはほとんどあり得ないことですが、何らかの理由で警察側の手続きに重大な瑕疵があった場合など、ごく例外的な状況が考えられます。しかし、これに期待することは現実的ではありません。
ステッカーが貼られた後の正しい対処法
ステッカーが貼られたら、以下のいずれかの対応が必要になります。
- 運転者が出頭する: 警察署に出頭し、交通反則告知書(青キップ)の交付を受け、反則金を納付します。この場合、運転者に違反点数が加算されます。
- 出頭しない(使用者が放置違反金を納付する): 後日、車両の使用者宛に放置違反金の納付書が送られてくるので、それで納付します。この場合、運転者に違反点数は加算されませんが、使用者に放置違反金の納付義務が生じます。
いずれにしても、金銭的な負担は発生します。「ステッカーを貼られたけれど罰金なし」という都合の良い状況は、基本的には期待できないと理解しておくべきです。駐車違反をしないことが最も重要です。
駐車違反の罰金はいくら?車種や場所で変わる?

「駐車違反をしてしまった場合、一体いくら罰金を支払う必要があるのだろう?」と不安に思う方は多いでしょう。駐車違反の「罰金」という言葉は一般的に使われますが、正確には運転者が出頭して納付する「反則金」と、出頭せずに車両の使用者が納付する「放置違反金」の2種類があります。これらの金額は、違反した場所や車両の種類によって細かく定められています。
駐車違反の種類と反則金・放置違反金の基本
駐車違反は、大きく分けて以下の2種類があります。
- 駐停車違反:
- 駐停車禁止場所(標識や道路標示で示された場所、交差点、横断歩道、トンネル内、坂の頂上付近など)での駐停車。
- 法定の駐停車禁止場所での駐停車。
- 放置駐車違反:
- 上記の駐停車違反のうち、運転者が車両を離れて直ちに運転できない状態にあるもの(客観的に見て放置されている状態)。これが一般的に「駐禁」として取り締まられるケースです。
通常、駐車違反で取り締まりを受けるのは「放置駐車違反」です。
反則金・放置違反金の金額(普通車の場合の例)
ここでは、最も一般的な普通車の場合の金額を例として示します。
| 違反の種類 | 場所区分 | 反則金(運転者が出頭) | 放置違反金(使用者が納付) |
|---|---|---|---|
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 15,000円 | 18,000円 |
| 駐車禁止場所等 | 12,000円 | 15,000円 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 12,000円 | ― |
| (運転者が直ちに移動できる場合など) | 駐車禁止場所等 | 10,000円 | ― |
※上記はあくまで一例であり、地域や具体的な状況によって異なる場合があります。必ずしも放置違反金の方が3,000円高いというわけではありませんが、一般的に放置違反金の方が高めに設定されています。
車種による金額の違い
反則金や放置違反金の額は、車両の種類によっても異なります。一般的に、大型車や中型車は普通車よりも高く、二輪車や原付は普通車よりも安く設定されています。
- 大型車・中型車(バス、トラックなど): 普通車よりも数千円程度高くなる傾向があります。
- 自動二輪車・原動機付自転車: 普通車よりも数千円程度安くなる傾向があります。
例えば、普通車の駐停車禁止場所等での放置駐車違反の反則金が15,000円の場合、大型車等では21,000円、二輪車では9,000円、原付では7,000円といった具合です(これもあくまで目安です)。
場所による金額の違い
「駐停車禁止場所等」と「駐車禁止場所等」で金額が異なります。
- 駐停車禁止場所等: 標識や標示で「駐停車禁止」とされている場所、交差点とその端から5メートル以内、横断歩道とその端から前後5メートル以内、バス停から10メートル以内など、より危険性が高いとされる場所です。こちらの方が罰則は重くなります。
- 駐車禁止場所等: 標識や標示で「駐車禁止」とされている場所、火災報知器から1メートル以内、駐車場の出入り口から3メートル以内などです。
ご自身の違反がどちらに該当するかは、現場の標識や道路標示、または警察官や駐車監視員からの説明、送付されてくる書類で確認する必要があります。
反則金の納付方法
運転者が出頭した場合、交通反則告知書(青キップ)と共に納付書が渡されます。金融機関(銀行や郵便局)の窓口で期限内に納付します。
放置違反金の納付方法
車両の使用者宛に「放置違反金納付命令書」と納付書が郵送されてきます。こちらも金融機関の窓口で期限内に納付します。
駐車違反の罰金は、決して安くはありません。違反をしないように心がけることが最も重要ですが、万が一違反してしまった場合は、速やかに正しい手続きを行いましょう。
駐車違反の点数と免許への影響!知っておくべきこと
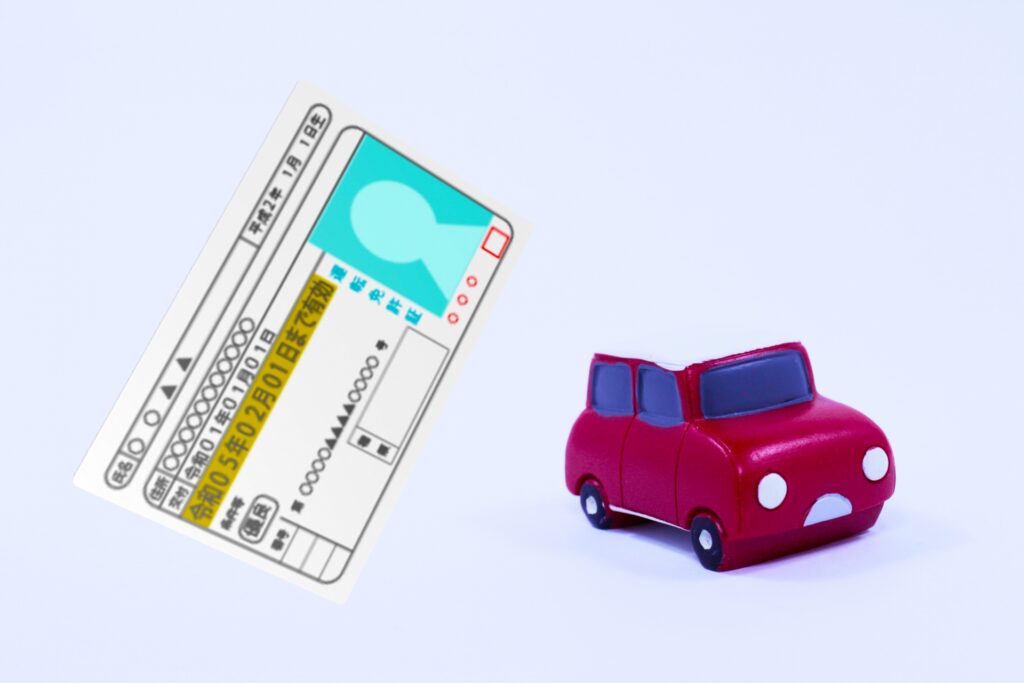
駐車違反でゴールド免許を失わないためには
多くのドライバーにとって、5年間無事故無違反の証である「ゴールド免許(優良運転者免許証)」は、誇りであり、保険料の割引など実質的なメリットもあるため、できる限り維持したいと考えるものです。しかし、うっかり駐車違反をしてしまった場合、このゴールド免許はどうなるのでしょうか。
駐車違反と違反点数
まず基本として、交通違反をすると内容に応じて「違反点数」が加算されます。ゴールド免許の条件は、過去5年間無事故無違反であることです。したがって、違反点数がつく違反をしてしまうと、次回の免許更新時にはゴールド免許ではなくなってしまいます(通常はブルー免許)。
駐車違反の場合、運転者が出頭して反則処理を受けると、違反点数が科されます。主な駐車違反の点数は以下の通りです。
- 駐停車禁止場所等での放置駐車違反: 3点
- 駐車禁止場所等での放置駐車違反: 2点
- 駐停車禁止場所等での駐停車違反: 2点
- 駐車禁止場所等での駐停車違反: 1点
※「放置駐車違反」は運転者が車から離れて直ちに運転できない状態、「駐停車違反」は運転者が乗車中または直ちに運転できる状態を指します。一般的にステッカーを貼られるのは「放置駐車違反」です。
点数がつかなければゴールド免許は維持できる?
ここで重要なのが、前述の「放置違反金制度」です。
運転者が出頭せず、車両の使用者(所有者など)が「放置違反金」を納付した場合、運転者自身には違反点数が科されません。違反点数がつかなければ、ゴールド免許の条件である「無事故無違反」は継続されるため、次回の免許更新時もゴールド免許を維持できる可能性が高くなります。
これが、「駐車違反をしても点数が引かれない方法」として知られ、ゴールド免許を維持したいドライバーが選択する理由の一つです。
放置違反金納付の注意点
ただし、この方法には注意が必要です。
- 放置違反金の納付は「違反がなかった」ことになるわけではない
あくまで運転者に対する行政処分(点数付加)が行われないだけで、車両の使用者は放置違反金を納付する義務を負います。 - 短期間に繰り返すと車両使用制限のリスク
ゴールド免許を維持したいがために、何度も放置違反金の納付を繰り返していると、前述の通り「車両使用制限命令」が出される可能性があります。こうなると、ゴールド免許云々の前に車が使えなくなるという大きなデメリットが生じます。 - 本当に「自分の違反」か?
家族や友人に車を貸していた際に駐車違反が発生した場合、使用者であるあなたが放置違反金を支払うことで点数を回避できますが、本来違反をした運転者の責任が問われないことになります。
ゴールド免許を維持するための最善策
ゴールド免許を確実に維持するための最善策は、言うまでもなく「駐車違反をしない」ことです。
- 駐車場を必ず利用する。
- 短時間でも路上駐車は避ける。
- 駐車禁止場所・駐停車禁止場所を正確に把握する。
万が一、駐車違反をしてしまい、放置車両確認標章が貼られた場合、ゴールド免許を維持したいという理由だけで安易に「出頭しない」を選択するのではなく、放置違反金のデメリット(金額が高い場合がある、車両使用制限のリスクなど)も十分に考慮し、総合的に判断する必要があります。
もし、ごく軽微な違反(例えば、点数が1点や2点の違反)で、他に違反歴がなく、次回のゴールド免許まで期間が十分にある場合などは、正直に出頭して反則金を納付し、点数を受け入れた方が、長期的に見て使用者としてのリスクを避けられる可能性もあります。
ゴールド免許の維持は大切ですが、それ以上に安全運転と法令遵守の意識を持つことがドライバーには求められます。
軽自動車も普通車と同じ?駐車違反の罰則

「軽自動車だから駐車違反の罰金は安いのでは?」「軽自動車なら取り締まりも甘いのでは?」といった疑問を持つ方がいるかもしれません。しかし、結論から言うと、軽自動車であっても駐車違反に関する基本的なルールや罰則は普通車と変わりません。
軽自動車の駐車違反:取り締まりの対象
道路交通法において、駐車違反の取り締まり対象となる車両に、普通車と軽自動車の区別はありません。軽自動車も四輪自動車の一区分であり、道路交通法が適用されます。
したがって、駐車禁止場所に駐車すれば、普通車と同様に放置車両確認標章(黄色いステッカー)が貼られ、反則金または放置違反金の対象となります。
反則金・放置違反金の金額
軽自動車の駐車違反における反則金や放置違反金の額は、普通車と比較して若干安く設定されている場合がありますが、決して「大幅に安い」わけではありません。普通車と同様に、違反した場所(駐停車禁止場所か、駐車禁止場所か)によって金額が変わります。
参考として、一般的な金額の目安を以下に示します(地域や具体的な状況により異なる場合があります)。
| 違反の種類 | 場所区分 | 普通車の反則金 | 軽自動車の反則金 | 普通車の放置違反金 | 軽自動車の放置違反金 |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 15,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 駐車禁止場所等 | 12,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
※2023年時点の情報に基づくと、多くの地域で軽自動車と普通自動車の放置駐車違反に関する反則金・放置違反金の額は同額となっているケースが多いようです。以前は区分があったこともありますが、現在は統一されている傾向にあります。正確な金額は、管轄の警察や送付される納付書で確認が必要です。
重要なのは、軽自動車だからといって罰則が大幅に軽減されるわけではないという点です。
違反点数
運転者が出頭して反則処理を受けた場合に科される違反点数についても、軽自動車と普通車で違いはありません。
- 駐停車禁止場所等での放置駐車違反:3点
- 駐車禁止場所等での放置駐車違反:2点
これらの点数が加算されれば、免許の色(ゴールド免許など)や免許停止・取り消しの基準に影響する点も普通車と同じです。
車両使用制限命令や車検拒否
放置違反金の納付を繰り返した場合の「車両使用制限命令」や、放置違反金を滞納した場合の「車検拒否制度」についても、軽自動車は普通車と同様に対象となります。
「軽自動車だから見逃してもらえるだろう」といった甘い考えは通用しません。
軽自動車の駐車で特に注意すべき点
軽自動車はそのコンパクトさから、狭いスペースにも駐車しやすいという利点があります。しかし、そのためにかえって安易な駐車をしてしまいがちになる側面も否定できません。
- 「少しの時間だから」「ちょっとだけなら」という油断が駐車違反につながりやすい。
- 歩道や路側帯への安易な乗り上げ駐車も厳禁。
都市部では、軽自動車専用のパーキングメーターや駐車場も増えてきていますが、そうした場所以外では、普通車と同様に駐車ルールを厳守する必要があります。
結論として、軽自動車も駐車違反に関しては普通車とほぼ同様の扱いを受けます。罰則の重さに大きな差はなく、違反をすれば相応のペナルティが科されることを理解し、常に交通ルールを遵守した運転を心がけましょう。
駐車違反の納付書が来ない場合の対処法

駐車違反をしてしまい、放置車両確認標章(黄色いステッカー)が貼られた後、運転者が出頭しなかった場合、車両の使用者宛に「放置違反金仮納付書」や「放置違反金納付命令書」(以下、まとめて「納付書」と呼びます)が郵送されてくるはずです。しかし、待てど暮らせど納付書が届かない場合、どうすればよいのでしょうか。
納付書が届くまでの一般的な期間
放置車両確認標章が貼られてから納付書が使用者のもとに郵送されるまでの期間は、一概には言えませんが、おおむね1週間から1ヶ月程度が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、警察の処理状況や郵送事情によって前後することがあります。
特に、年度末や大型連休前後などは、処理が遅れる可能性も考えられます。
納付書が来ない場合に考えられる理由
- 処理の遅延
最も多いケースは、警察内部での事務処理や郵送手続きに時間がかかっている場合です。特に都市部や違反が多い地域では、処理件数が多く遅れが生じやすいことがあります。 - 使用者情報の確認に時間がかかっている
車両の登録情報(車検証情報)と現住所が異なる場合(引越し後に住所変更手続きをしていないなど)や、リース車両、法人名義の車両などで使用者特定に時間を要している可能性があります。 - 郵送事故
稀なケースですが、郵便物が何らかの理由で届かない(誤配、紛失など)可能性もゼロではありません。 - 既に運転者が出頭・処理済み
同居家族などが運転していて、既に警察に出頭して反則金の手続きを済ませている場合、使用者宛には放置違反金の納付書は送られてきません。 - ごく軽微な違反で警告に留まった(極めて稀)
現実的にはほとんどありませんが、状況によっては警告のみで処理されるケースが万が一あったとしても、それは期待すべきではありません。
納付書が来ない場合の対処法
- まずは一定期間待つ
ステッカーが貼られてから1ヶ月程度は、焦らずに待ってみましょう。特に心配な場合は、1ヶ月半~2ヶ月程度を目安にしてもよいかもしれません。 - 車両の登録情報を確認する
車検証に記載されている使用者の氏名・住所が最新のものになっているか確認しましょう。引越しなどで変更があった場合は、速やかに運輸支局等で変更手続きを行う必要があります。これが原因で届いていない可能性もあります。 - 警察に問い合わせる
一定期間待っても納付書が届かない場合は、違反行為を行った場所を管轄する警察署の交通課、または放置車両確認標章に記載されている問い合わせ先(都道府県警察の専用窓口など)に電話で問い合わせてみましょう。問い合わせる際は、以下の情報を準備しておくとスムーズです。- 車両のナンバー(登録番号)違反した日時と場所(おおよそでも可)放置車両確認標章に記載されている標章番号(分かれば)車検証記載の使用者氏名、住所
- 放置は絶対にしない
「納付書が来ないから支払わなくてラッキー」と考えるのは非常に危険です。放置違反金には納付期限があり、それを過ぎると延滞金が加算される可能性があります。さらに長期間滞納すると、督促状が送付され、最終的には財産の差し押さえに至ることもあります。納付書が来ないからといって放置せず、必ず上記の対応を取りましょう。
問い合わせ時の注意点
- 感情的にならず、冷静に状況を説明しましょう。
- 警察も多数の案件を処理しているため、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
- 問い合わせの記録(日時、担当者名、回答内容など)をメモしておくと、後で役立つことがあります。
納付書が届かない場合でも、放置せずに適切な対応を取ることが重要です。まずは待ち、それでも届かなければ速やかに警察に確認しましょう。
駐車違反の点数はいつ消える?リセット条件

駐車違反をしてしまい、運転者が出頭して反則点数が科された場合、その点数はいつ消えるのでしょうか。また、点数がリセットされる条件はあるのでしょうか。これらの知識は、免許の更新や将来の運転に影響するため、正しく理解しておくことが重要です。
違反点数の基本的な仕組み
交通違反をすると、その内容に応じて基礎点数が付与され、過去3年間の累積点数によって免許停止や取り消しといった行政処分が行われます。
点数は加算方式で累積していきますが、一定の条件を満たすと、それまでの点数が計算上リセットされる(累積されなくなる)ことがあります。
点数が消える(リセットされる)主な条件
違反点数が実質的に「消える」、つまり行政処分の計算対象から除外される主なケースは以下の通りです。
- 最後の違反から1年間無事故・無違反
ある違反をした後、その日から1年間、新たな違反(点数がつくもの)をせず、かつ事故も起こさなかった場合、それ以前の違反点数は累積計算されなくなります。これが最も一般的なリセット条件です。- 例: 2024年5月1日に2点の駐車違反。その後、2025年5月1日まで無事故無違反であれば、この2点は累積されなくなります。
- 免許の停止処分(免停)を受けた場合
違反点数が一定基準に達し、免許停止処分を受けた場合、その処分の原因となった点数は、処分終了後には累積されなくなります。ただし、処分歴(前歴)として記録は残ります。前歴があると、次に少ない点数で免許停止になるなど、不利な扱いを受けることになります。- 注意: 免停期間が終了すれば点数がゼロになるわけではなく、その免停の原因となった点数が計算対象外になるという意味です。免停期間中にさらに違反をすれば、それは新たな点数として加算されます。
- 2年間無事故・無違反で、かつ2点以下の軽微な違反1回のみの場合
過去2年間無事故・無違反の人が、2点以下の軽微な違反(例:駐車禁止場所での放置駐車違反など)を1回だけした場合、その違反から3ヶ月間さらに無事故・無違反であれば、その軽微な違反の点数は累積されなくなります。- 例: 長年無事故無違反だった人が、2024年5月1日に2点の駐車違反。その後、2024年8月1日まで無事故無違反であれば、この2点は累積されなくなります。これは「3ヶ月特例」などと呼ばれることがあります。
- 免許の取り消し処分を受けた場合
免許取り消し処分を受けると、それまでの違反点数や前歴は全てリセットされます。ただし、再度免許を取得するには欠格期間(免許を取れない期間)があり、その後改めて教習所に通うか試験を受ける必要があります。
点数が「消える」わけではない点に注意
重要なのは、上記の条件を満たしても、違反の事実そのものが記録から抹消されるわけではないということです。あくまでも、行政処分(免許停止や取り消し)の基準となる累積点数の計算において、加算されなくなるという意味です。
運転免許経歴証明書などを取得すると、過去の違反歴は記載されます。
ゴールド免許との関連
ゴールド免許の条件は「過去5年間無事故・無違反」です。上記の点数リセット条件を満たしても、違反した事実があれば、その日から5年間はゴールド免許の対象外となります。
例えば、1年間無事故無違反で点数がリセットされても、その違反日から5年間はブルー免許になるのが一般的です。
点数制度を正しく理解するために
- 自分の違反点数を確認する
累積点数が気になる場合は、「運転記録証明書」を自動車安全運転センターで申請・取得することで確認できます。 - 無事故・無違反を心がける
点数制度を気にする以前に、安全運転を心がけ、違反をしないことが最も大切です。 - 処分を受けた場合は指示に従う
免許停止などの処分を受けた場合は、その指示に誠実に従いましょう。
駐車違反による点数も、他の交通違反と同様に扱われます。点数がいつ消えるか、リセットされるかの条件を正しく理解し、安全運転に努めましょう。
駐車違反の疑問を解消!「Yahoo!知恵袋」から学ぶ注意点
駐車違反に関して疑問や不安を抱いたとき、Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで情報を探す人は少なくありません。そこには実体験に基づいた様々な質問や回答が寄せられており、参考になる情報も確かに存在します。しかし、一方で誤った情報や不確かな情報も散見されるため、鵜呑みにするのは危険です。
ここでは、「知恵袋」などでよく見られる駐車違反に関する疑問や、それらに対する正しい考え方、注意点を解説します。
「知恵袋」でよく見る駐車違反の疑問と注意点
- Q駐車違反のステッカー、無視しても大丈夫?
- A
「自分は無視してたら何も来なかった」「しばらくしたら忘れた頃に督促状が来た」
注意点と正しい理解
放置車両確認標章(ステッカー)を無視しても、違反の記録は警察に残っています。運転者が出頭しなければ、車両の使用者宛に放置違反金の納付書が送られてきます。これを無視し続けると、延滞金が加算され、最終的には財産差し押さえに至る可能性があります。「何も来なかった」というケースは非常に稀か、あるいは記憶違い、郵送トラブルなどが考えられます。無視は絶対にNGです。
- Q「出頭しないで放置違反金を払えば点数はつかないって本当?」
- A
「本当です。ゴールド免許維持できます」「友達もそうしてる」
注意点と正しい理解
これは制度上その通りで、運転者が出頭せず使用者が放置違反金を納付すれば、運転者に違反点数は科されません。しかし、知恵袋の回答では、放置違反金のデメリット(反則金より高額な場合がある、繰り返すと車両使用制限命令のリスクなど)が十分に説明されていないことがあります。メリットだけでなくデメリットも理解することが重要です。
- Q「短時間なら駐車しても大丈夫?」
- A
「5分くらいなら見逃してくれることもある」「監視員が見てなければ大丈夫」
注意点と正しい理解
駐車禁止場所に駐車すれば、時間の長短にかかわらず駐車違反となります。駐車監視員は効率的に巡回しており、「少しの時間だから」という油断が命取りになることも。また、駐車が許されるのは「停車」の定義(人の乗り降りのための停止、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止で、運転者がすぐに運転できる状態)に合致する場合のみであり、それ以外は駐車とみなされます。時間の問題ではありません。
- Q「納付期限が過ぎてしまったらどうなる?」
- A
「すぐに払えば大丈夫」「延滞金がつくかも」
注意点と正しい理解
納付期限を過ぎると、まず督促状が送られてくるのが一般的です。延滞金が加算されることもあります。さらに放置すると、財産差し押さえの対象となる可能性があります。期限を過ぎてしまった場合は、速やかに納付書に記載されている問い合わせ先に連絡し、指示を仰ぎましょう。
- Q「弁明書を出せば違反金は免除される?」
- A
「理由をしっかり書けば大丈夫なこともある」「ほとんど無理」
注意点と正しい理解
弁明が認められるのは、盗難や災害など、使用者や運転者に責任がないと客観的に証明できる極めて限定的なケースです。「知らなかった」「急いでいた」などの理由は通常認められません。過度な期待は禁物です。
「知恵袋」情報を活用する際の心構え
- 情報の真偽を確認する: 知恵袋の回答は個人の経験や主観に基づくものが多く、必ずしも正確とは限りません。複数の情報源(警察の公式サイト、交通法規の専門サイトなど)で裏付けを取ることが大切です。
- 最新の情報を確認する: 法律や制度は改正されることがあります。古い情報がそのままになっている可能性もあるため、情報の更新日などを確認しましょう。
- 専門機関に相談する: 不明な点や不安なことがある場合は、安易にネットの情報だけで判断せず、管轄の警察署や弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。
- 自己責任で判断する: 最終的な判断は自分自身で行う必要があり、その結果についても責任を負うことになります。
知恵袋は手軽に情報を得られる便利なツールですが、駐車違反のような法的な問題に関しては、情報の取捨選択と確認作業が不可欠です。正しい知識を身につけ、適切に対処しましょう。
【総括】駐車違反で点数が引かれないための重要ポイント
参考
交通違反の点数一覧表(警視庁)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
反則行為の種別及び反則金一覧表(警視庁)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html
道路交通法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
自動車安全運転センター http://www.jsdc.or.jp/